結婚を決意したものの、新生活のスタートにかかる費用に不安を感じていませんか?
「結婚式や新居の費用が足りない…」
「計画的な貯金をしていなかったから心配…」
といった悩みは、多くの新婚カップルが抱える問題です。
私も、結婚を決断するまでが早く、計画的な貯金などをしていなかったため、最初はかなり金銭的に厳しい状態でした。
そんな経験があるからこそ、この補助金がどれほど新婚カップルの経済的負担を軽減してくれるか痛感しています。
この記事は、あなたが最後まで読みたくなる、補助金についてのコンテンツです。
- 結婚を考えている方
- 特に結婚資金に不安がある方
に向けて、国や自治体が実施している結婚新生活支援事業(結婚新生活補助金)について、記事を作成しました。
令和7年度(2025年)の最新情報に基づき、
- 補助金の対象となる世帯の条件
- 支給金額
- 申請方法
- 必要書類
まで、すべてを徹底解説します。
これを読めば、あなたが新生活の費用を心配することなく、結婚という新たなスタートを安心して切れるようになるはずです。
さあ、賢く補助金を活用して、理想の新婚生活を手に入れましょう。
結婚新生活補助金とは?概要を解説
結婚新生活補助金とは、少子化対策の一環として、結婚に伴う新生活の経済的負担を軽減するために国が支援し、自治体が実施している事業です。
- 新婚カップルが新居を購入したい
- 賃借したい
こんな時に発生する費用。
引越費用などを補助してくれます。
令和7年度(2025年)の情報を中心に、その概要を紹介します。
国の「地域少子化対策重点推進交付金」
この補助金の主となる財源は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」です。
これは、地域における少子化対策を推進するために、自治体が実施する結婚・子育てを支援する事業に交付されるものです。
- 事業目的: 結婚を希望する方への経済的支援を通じて、少子化対策を推進する。
- 対象: 各自治体の定める要件を満たす新婚夫婦。
- 内容: 新居の購入費用や賃借費用(家賃、敷金、礼金、仲介手数料、共益費)、引越費用などを補助。
自治体ごとの実施状況と注意点
結婚新生活補助金は、国の支援を受けていますが、実際の事業の実施は各自治体(市町村)に委ねられています。
そのため、対象となる条件や支給金額、申請期間などが自治体ごとに異なります。
- 情報確認: 申請を検討する際は、必ずご自身の居住する自治体のホームページなどで最新情報を確認してください。
- 予算: 補助金には予算額があります。予算額に達した場合は期間内であっても受付が終了する可能性があります。早めの確認と申請がおすすめです。

補助金の対象者と主な条件
結婚新生活補助金を受け取るためには、夫婦それぞれに年齢や所得などの条件が定められています。
ご自身が対象者に該当するかどうか、詳細を確認しましょう。
夫婦の年齢と婚姻日
対象となる世帯の条件として、夫婦の年齢と婚姻の時期が重要です。
- 年齢: 申請をする時点で、夫婦ともに39歳以下であることが基本です(令和7年4月1日の時点で39歳以下)。自治体ごとに29歳以下など、さらに年齢が低い条件を設けている場合もあります。
- 婚姻期間: 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届が受理された世帯が対象となる場合が多いです。申請の期間と合わせて確認が必要です。
世帯所得と居住要件
補助金の対象となる世帯には、所得に関する上限も設けられています。
- 世帯所得: 夫婦の所得を合算して500万円未満であることが一般的な条件です。ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その年間返済額を所得から控除できる場合があります。
- 居住要件: 申請する自治体に居住していることが必要です。新居の住所が自治体の要件を満たしているか確認しましょう。

支給される補助金額と対象経費
結婚新生活補助金で実際に受け取れる金額と、どのような費用が補助の対象になるのかを詳しく解説します。
上限額や対象となる期間など、重要な情報を確認しましょう。
支給額の上限
補助金の支給額には上限があります。
- 夫婦ともに29歳以下の場合: 上限 60万円
- 夫婦のいずれかが30歳以上39歳以下の場合: 上限 30万円
- 注: これらの金額は国の目安であり、自治体ごとに異なる場合があります。
補助の対象となる経費
補助金の対象となる経費は、主に以下の費用です。
- 住居費
- 新居の購入費用
- 新居の賃借費用(敷金、礼金、仲介手数料、共益費、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った家賃1年分など)
- リフォーム費用(新居の取得または賃借に伴う改修)
- 引越費用
- 引越業者や運送業者に支払った費用
- その他引越しに係る費用(一部自治体で対象となる場合あり)
対象外となる費用
以下の費用は基本的に対象外となります。
- 家具・家電購入費用
- 敷金・礼金などを返済される場合
- 賃貸借契約書の契約期間が1年未満の場合
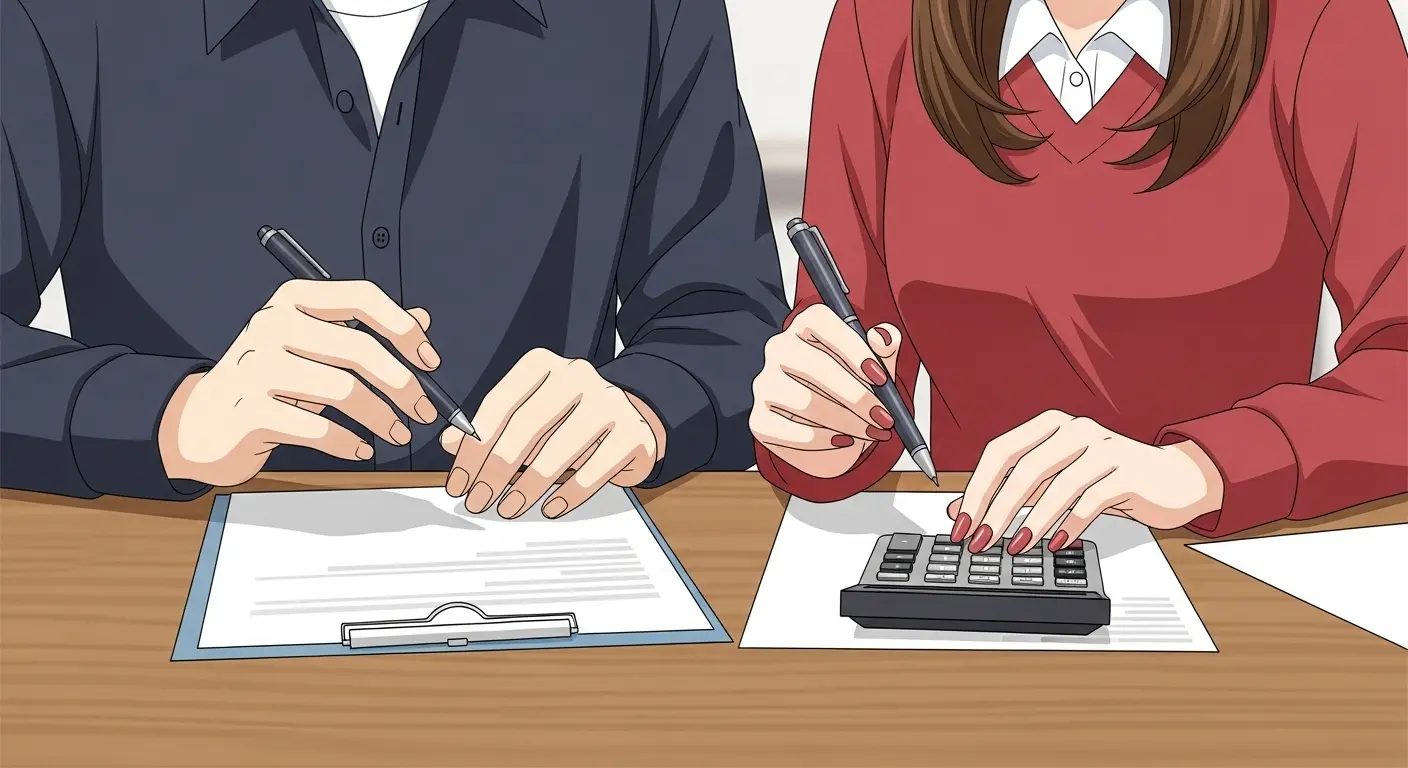
申請方法と必要書類
結婚新生活補助金を受け取るためには、必要書類を揃えて申請手続きを行います。
自治体ごとに申請方法や必要書類が異なる場合があります。
ご自身の自治体の案内を必ず確認してください。
申請の基本的な流れ
補助金の申請は、一般的に以下の流れで行われます。
- 情報収集: ご自身の居住する自治体のホームページで、結婚新生活支援事業の詳細を検索し、対象となる条件や必要書類、受付期間を確認します。
- 書類準備: 申請に必要な書類をすべて揃えます。
- 申請提出: 必要書類を揃えて、自治体の窓口(担当課)に提出します。郵送での提出が可能な自治体もあります。
- 審査: 提出された書類に基づき、審査が行われます。
- 交付決定: 審査が通れば、交付決定の通知が送られてきます。
- 補助金支給: 指定の口座に補助金が支給されます。
必要書類一覧(一般的な例)
自治体ごとに異なる場合がありますが、一般的に必要となる書類は以下の通りです。
- 結婚新生活支援事業補助金交付申請書(自治体ホームページからダウンロード)
- 住民票の写し(夫婦それぞれのもの)
- 戸籍謄本(婚姻情報が記載されたもの)
- 所得証明書(夫婦それぞれのもの)
- 貸与型奨学金の返済がわかる書類(該当する場合)
- 住居費用の支払ったことを証明する書類(領収書、賃貸借契約書、売買契約書の写しなど)
- 引越費用の支払ったことを証明する書類(領収書など)
書類作成のポイント
- 記載漏れや不備がないよう、申請書は丁寧に記入しましょう。
- 領収書や契約書は、日付や金額、支払った相手などが明確に記載されていることを確認してください。

よくある質問と注意点
結婚新生活補助金に関するよくある質問や、申請時の注意点をまとめました。
疑問を解決し、スムーズな申請に繋げましょう。
- Q: 賃貸借契約書の契約期間が1年未満でも対象になりますか?
- A: 基本的に対象外です。補助金の対象となる住居は、居住の安定性が求められるため、賃貸借契約書の契約期間が1年以内であることが条件となる場合が多いです。
- Q: 家賃は1年分しか対象にならないのですか?
- A: はい、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った家賃の合計金額が補助金の対象となります。この期間以外に支払った家賃は対象外です。
- Q: 結婚する前に支払った費用も対象になりますか?
- A: 婚姻届が受理された日から1年以内に支払った費用が対象となる場合が多いです。自治体ごとに対象期間が異なりますので、必ず確認してください。
- Q: 所得の計算で夫婦どちらかの所得が高い場合でも大丈夫ですか?
- A: 夫婦の所得を合算して上限額(500万円未満など)を満たしていれば問題ありません。ただし、貸与型奨学金の返済がある場合は、返済額を所得から控除できるため、対象となる可能性もあります。
申請時の注意点
- 期間内申請: 申請期間は厳守です。期間を過ぎてしまうと、申請は受け付けられません。早めの準備と提出を心がけましょう。
- 予算額に注意: 補助金には予算額があり、予算額に達し次第終了となる可能性があります。自治体のホームページで受付状況を確認しましょう。
- 情報の正確性: 提出する書類の情報に不備や虚偽があると、審査に通らないだけでなく、不正受給とみなされる可能性もあります。正確な情報を記載しましょう。
- 問い合わせ: 不明な点があれば、自治体の担当窓口に直接問い合わせるのが最も確実です。

地域別!結婚新生活補助金制度の探し方と具体例
結婚新生活補助金は自治体ごとに内容が異なります。
ご自身の居住する地域でどのような制度が実施されているかを効率的に探す方法と、いくつかの具体例を紹介します。
自治体ホームページでの探し方
最も確実なのは、ご自身の居住する市町村のホームページで検索することです。
- 検索キーワード例: 「(お住まいの市町村名) 結婚新生活補助金」「(お住まいの市町村名) 結婚新生活支援事業」
- 確認すべき項目: 対象者の要件(年齢、所得、婚姻期間など)、補助金額の上限、対象経費、申請期間、必要書類、申請窓口(担当課の電話番号など)
補助金制度の具体例
ここでは、例としていくつかの自治体の制度を紹介します。
これらはあくまで例であり、最新情報は必ず各自治体の公式サイトで確認してください。
- 東京都: 一部の区や市で独自の結婚新生活支援事業を実施している場合があります。
- 大阪府: 大阪市を含む一部市町村で、新婚世帯の住居費用や引越費用を補助する制度を設けていることがあります。
- 地方自治体: 少子化対策に力を入れている地方の自治体では、手厚い補助金を用意している場合が多いです。移住を検討している方は、移住支援制度と合わせて確認するのも良いでしょう。
- 参考サイト: 地域少子化対策重点推進交付金 実施計画(子ども家庭庁のサイト)

申請に必要な書類の具体的な準備と注意点
結婚新生活補助金の申請には、様々な書類の提出が必要です。
正確かつスムーズな手続きのために、それぞれの書類の準備のポイントと注意点を詳しく解説します。
住民票・戸籍謄本の発行
- 住民票: 夫婦それぞれの住民票が必要です。本籍や世帯主の記載が必要な場合もあるので、申請する自治体の要件を確認しましょう。市役所や区役所の窓口、またはコンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できます。
- 戸籍謄本: 婚姻情報が記載された戸籍謄本が必要です。本籍地の役所で取得します。郵送での取得も可能ですが、時間がかかる場合があるので早めに手配しましょう。
所得証明書の取得
- 所得証明書: 夫婦それぞれの所得証明書が必要です。これは、前年の所得を証明するもので、市役所や区役所の課税課などで取得できます。源泉徴収票や確定申告書の写しで代用できる場合もありますが、自治体の指示に従いましょう。
- 注意点: 取得できる時期が限られている場合があるので、事前に確認し、早めに取得してください。
賃貸借契約書・売買契約書・領収書
- 賃貸借契約書または売買契約書の写し: 新居の契約が確認できる書類です。契約期間、契約者名、住所、金額などが明確に記載されていることを確認しましょう。
- 領収書: 敷金、礼金、仲介手数料、引越費用などの支払いを証明する領収書が必要です。宛名、日付、金額、但し書きが明確に記載されているものを用意してください。
- 注意点: 支払ったことを証明できるものが必要なので、必ず領収書を発行してもらいましょう。クレジットカードの利用明細書などでは代用できない場合が多いです。

審査をスムーズに進めるためのポイント
結婚新生活補助金の申請後、自治体による審査が行われます。
審査をスムーズに進めるためには、いくつかのポイントがあります。
申請書の記入例と確認事項
- 記入例の確認: 多くの自治体は、ホームページに申請書の記入例を掲載しています。記入例を参考に、正確に記載しましょう。
- 不備の確認: 申請書を提出する前に、必要な項目がすべて記入されているか、誤字脱字はないか、添付書類はすべて揃っているかなどを徹底的に確認してください。
- 担当者への問い合わせ: 不明な点があれば、申請窓口の担当者に電話やメールフォームで問い合わせて解決しましょう。
審査期間と結果通知
- 審査期間: 審査期間は自治体ごとに異なる場合がありますが、通常は数週間から1ヶ月程度かかる場合が多いです。申請が集中する時期は、さらに時間がかかる可能性もあります。
- 結果通知: 審査が完了すると、交付決定の通知または不交付決定の通知が郵送されます。交付決定通知書には、支給金額や振込時期などが記載されています。
- 不交付の場合: 不交付決定となった場合でも、理由が記載されています。内容を確認し、必要であれば自治体に問い合わせましょう。
申請の進捗状況確認
- 進捗確認: 申請後、審査の進捗状況を確認したい場合は、申請した自治体の担当課に電話で問い合わせてみましょう。その際、申請番号や世帯の情報を伝えられるように準備しておくとスムーズです。

結婚新生活補助金Q&A(追加のよくある質問)
結婚新生活補助金に関する、さらに詳しく知りたいことや、特に注意すべき点について、Q&A形式で解説します。
審査基準に関する質問
- Q: 所得の計算で夫婦どちらか一方が所得がない場合でも対象になりますか?
- A: はい、夫婦の所得を合算した金額が上限額未満であれば対象となります。どちらか一方に所得がない場合でも、世帯としての所得が要件を満たしていれば問題ありません。
- Q: 過去に補助金を受け取ったことがある場合、再申請は可能ですか?
- A: 基本的に不可能です。結婚新生活支援事業は、原則として1世帯につき1回限りの支給となります。過去に同一世帯で補助金を受給した場合は対象外です。
申請期間と予算に関する質問
- Q: 申請はいつまでできますか?
- A: 令和7年度の事業は、令和8年3月31日までに申請を完了する必要がある場合が多いです。ただし、予算額に達し次第終了となるため、早めの申請が重要です。
- Q: 予算が終了したら、来年度も実施されますか?
- A: 国の政策や自治体の予算によって異なります。例年実施されている自治体も多いですが、確実な情報は毎年更新される自治体のホームページで確認してください。

結婚新生活補助金以外の支援制度
結婚新生活補助金の他にも、新婚カップルの新生活を支援する制度はいくつか存在します。
これらの制度も活用することで、さらなる経済的負担の軽減に繋がる可能性があります。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)
新居を購入する場合に利用できる制度です。
- 概要: 住宅ローンの年末残高の一定割合を、所得税から控除できる制度です。新婚夫婦で住宅ローンを組む場合、大きな控除が受けられる可能性があります。
- 対象者: 所得や住宅の条件など、詳細な要件があります。
- 確認先: 国税庁のホームページなどで確認しましょう。
- 参考: 国税庁 住宅借入金等特別控除
各種手当・給付金
結婚後、出産や子育てを伴う場合には、様々な手当や給付金を受け取れる可能性があります。
- 出産育児一時金: 健康保険から支給される出産に係る費用の補助です。
- 児童手当: 子育て世帯に支給される手当です。
- その他: 自治体ごとに独自の子育て支援制度や助成金がある場合があります。

まとめ:賢く活用して、最高の新婚生活を!
結婚新生活補助金は、新婚カップルの新生活を経済的に応援してくれる貴重な制度です。
私自身も計画的な貯金がない状態で結婚を決断した経験から、この補助金が新生活のスタートにどれほど役立つかを実感しています。
この記事で解説した内容を参考に、
- 補助金の概要
- 対象者の条件
- 支給金額
- 申請方法
- 必要書類
- そしてよくある質問や注意点
をしっかり確認してください。
自治体ごとに詳細が異なるため、必ずご自身の居住する市町村の最新情報を確認することが重要です。
最大60万円という金額は、新居の初期費用や引越費用の大きな助けになります。
この補助金を賢く活用することで、金銭的な不安を軽減し、理想の新婚生活をスムーズにスタートできるでしょう。
結婚は、人生における大きな節目であり、新生活は夫婦の絆を深める大切な時間です。
補助金の情報を役立てて、経済的な心配を減らしましょう。
新郎新婦が笑顔で最高の新婚生活を送れることを心から願っています。
ぜひ今すぐ、ご自身の自治体の制度を確認してみてください。
申請前の最終チェックリスト
結婚新生活補助金の申請を行う前に、最後の確認を行いましょう。
漏れがないか、すべての項目をチェックしてください。
申請要件の再確認
- 夫婦の年齢は上限を満たしていますか?
- 婚姻届の受理日は対象期間内ですか?
- 世帯所得は上限額未満ですか?(奨学金控除も考慮)
- 新居の住所は自治体の要件を満たしていますか?
- 対象となる経費はすべて支払って、領収書がありますか?
必要書類の完璧な準備
- 申請書: 記入漏れ、誤字脱字はないですか?
- 住民票: 夫婦それぞれの最新版を取得しましたか?
- 戸籍謄本: 婚姻情報が記載されたものを取得しましたか?
- 所得証明書: 夫婦それぞれの最新版を取得しましたか?
- 賃貸借契約書/売買契約書: 写しを用意し、必要な情報が明確ですか?
- 領収書: すべての対象経費の領収書を揃えましたか?
- その他書類: 自治体が指定する他の書類はすべて揃いましたか?
申請方法と提出先の確認
申請方法: 郵送、オンライン、窓口持参のいずれですか?
提出先: どの課の窓口に提出しますか?
受付期間: 申請期間の締め切りを確認しましたか?(予算終了の可能性も考慮)

お問い合わせ先と関連情報
結婚新生活補助金に関する疑問や確認事項がある場合は、自治体の担当窓口に直接問い合わせるのが最も確実です。
各自治体の担当窓口
ご自身の居住する市町村の役所のホームページを確認しましょう。
結婚新生活支援事業の担当課の連絡先(電話番号やメールフォームなど)を検索してください。
問い合わせの際は、ご自身の状況(夫婦の年齢、所得、新居の種類など)を明確に伝えられるように準備しておくと、スムーズに案内を受けられるでしょう。
関連する国の支援事業
内閣府: 地域少子化対策重点推進交付金の概要や、各自治体の実施計画が掲載されている場合があります。
厚生労働省: 子育て支援に関する情報も確認できます。
結婚新生活補助金Q&A(地域差と制度の今後)
結婚新生活補助金の地域差や、今後の制度の動向について、さらに深く掘り下げて解説します。
地域ごとの制度の違い
- 対象者の細分化: 所得や年齢の条件が、国の目安より厳しく設定されている自治体もあれば、より柔軟な条件を設けている自治体もあります。例えば、共働き世帯への配慮や、子育て世帯への加算など。
- 独自の加算: 一部の自治体では、特定の地域への移住や、子育てとの両立を支援するための独自の加算制度を設けている場合があります。
- 申請期間: 自治体の予算サイクルや事業計画によって、申請期間が短く設定されている場合や、年度途中で受付を終了する場合もあります。
制度の継続と将来性
- 国の少子化対策: 結婚新生活補助金は、国の重要な少子化対策の一つとして位置づけられています。今後も制度が継続される可能性は高いですが、社会情勢や政策の優先順位によって見直しが行われることも考えられます。
- 自治体の役割: 国からの交付金を受け実施される事業であるため、自治体の予算状況や政策の方向性が制度の継続や内容に大きな影響を与えます。
